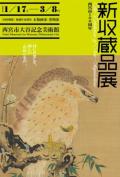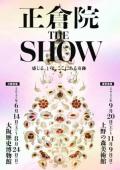ホーム > チケットプレゼント
ここから本文です。
チケットプレゼント
検索条件 プレゼント:全て
16件中 1~10件表示 表示件数
![]()
![]()
サラ・モリス(1967年生まれ)は幅広い創作活動を行うニューヨーク在住のアーティストです。国際的に高い評価を受けるモリスは、図式的なグリッドを用いた幾何学的な抽象絵画で知られています。1990年代以降、モリスは絵画、映像、壁画、ドローイング、彫刻など、多様な作品を制作してきました。それらの作品には、ネットワーク、タイポロジー、建築、都市への関心が反映されています。 モリスは大阪中之島美術館と関わりが深いアーティストです。大阪中之島美術館は、モリスの作品を日本で初めてコレクションに加えた美術館であり、所蔵作品にはモリスの大型絵画や映像作品《サクラ》があります。 「サラ・モリス 取引権限」は日本初となるモリスの大規模個展です。本展では、モリスの30年以上にわたるキャリアの中で生み出された作品を100点近く展示します。展示作品には、絵画はもちろん、映像作品全17点やドローイング、本展のため制作される大型の壁画が含まれます。2018年、桜の開花直前に関西などで撮影された《サクラ》も展示されます。
![]()
![]()
大横尾辞苑は、ひらがな45文字(あ〜を)、およびアルファベット26文字(A〜Z)にそれぞれ対応する、横尾忠則の作品世界に関連する用語を選び、それらにちなんだ作品や資料から構成した、「辞書」仕立ての展覧会です。 横尾忠則は様々な事象に興味を抱く、まさに博覧強記の人です。森羅万象あらゆるものを貪欲に作品のモチーフにする姿勢は、ある意味「百科全書」的といえるかもしれません。今回選定した用語は、必然的にその興味を反映したものとなりました。横尾の人生を彩るエピソードや、交友関係を反映したものもあれば、科学のみでは捉えきれない精神世界や、死の問題に関するものも数多く収録されています。 この「辞書」が、横尾忠則の作品世界をより深く知るだけでなく、我々がより深く、豊かな人生を送るささやかな一助となれば幸いです。
![]()
![]()
古来より多くの温泉に恵まれた兵庫。 信仰と結びつきながら見いだされた温泉は、やがて療養の場から名所、観光地へと変わっていきました。そして、人々が温泉に求めるものを反映して、温泉をとりまく“まち”もその姿を変化させていきます。本展では、温泉を中心に発展してきた4つの“温泉まち”を取り上げます。 霊場として信仰を集めた温泉寺を中心に、天下人の庇護を得ながら発展した有馬。信仰にもとづく独特の入浴作法と外湯めぐりで人気を博した城崎。風情のある旅館が立ち並ぶ「旧温泉」と家族で楽しむモダンな「新温泉」が対照的な宝塚。高温の「荒湯」を利用した湯がき文化や、テレビドラマの舞台となったことでも知られる湯村。 それぞれのまちの歴史を交えながら、地域の特性を活かして育まれた豊かな温泉文化を紹介します。
![]()
![]()
豊かな自然に恵まれた風光明媚な土地柄と、神社仏閣をはじめ歴史的な景観が点在する奈良は、古くから詩歌や文学、芸術の題材とされ、文人たちをも魅了する憧憬の地として知られてきました。明治時代に入ると、信仰と結びついた奈良の文化が改めて評価される中で、美術や行政に携わる人たちが盛んに訪れるようになり、古都・奈良の地にも徐々に新時代の息吹が芽生え始めます。大正時代から昭和戦前期にかけては、奈良の歴史や文化財に関する調査・研究も進展し、その魅力が広く浸透するとともに多くの文化人が集い、往来するようになりました。また、こうした動向は奈良の人々をも刺激して、両者は互いに交流を重ねながら時にはコミュニティーを形成し、地域文化の興隆を促しました。 本展では、美術家をはじめ研究者や文学者から美術行政家まで、奈良に足跡を残した人々を、「第1章 近代の息吹~對山楼に宿る人々」、「第2章 華開くモダン~高畑界隈の人々」の2章により紹介します。美術を通じて展開された、これら文化人たちの活動を概観することで、奈良と美術との関わりを検証すると同時に、独自の文化が華開いた近代奈良の一面に目を向ける機会となれば幸いで…
![]()
![]()
大阪歴史博物館では、令和8年(2026)1月16日(金)から3月15日(日)まで、特別企画展「河内源氏と壺井八幡宮」を開催します。 「八幡太郎」源義家や、源頼朝・義経兄弟、足利尊氏を輩出した「河内源氏」。そのはじまりは、義家の祖父・源頼信が河内国壺井(現大阪府羽曳野市壺井)の地に館を建てたことに遡ります。頼信の子・頼義が石清水八幡宮を勧請して建立した壺井八幡宮は、源氏の守護神として長らく武家の崇敬を受け、現在に至っています。 本展では、「木造僧形八幡神及諸神坐像」「黒韋威胴丸(壺袖付)」(いずれも重要文化財)、「太刀 銘安綱(号 天光丸)」(重要美術品)をはじめとする壺井八幡宮の社宝と、河内源氏に関する館蔵資料等をあわせて展示し、「武士の世」の礎を築いた河内源氏の活躍と伝承、そしてその源流が大阪にあったことをご紹介します。
16件中 1~10件表示 表示件数